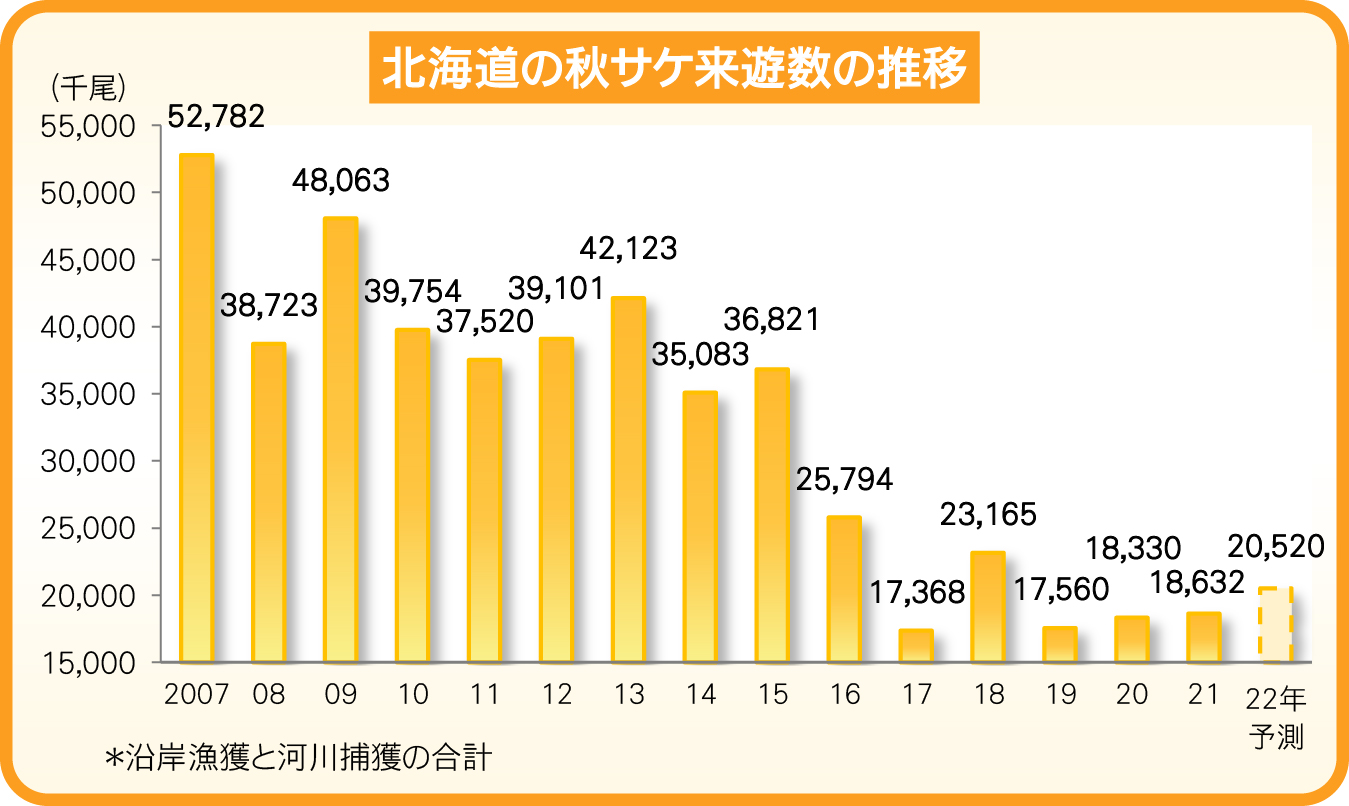山口県下関市の沖合底引網船団が今漁期から全船で導入した漁獲アプリで水揚げ情報のデジタルデータ化を実現し、魚価向上の効果が表れ始めた。下関漁港(同市)を基地とする山口県以東機船底曳網漁業協同組合(宮本洋平組合長)の沖合底引船団(5カ統10隻)は今漁期入りした2021年8月15日から専用の漁獲情報アプリを全船に導入。これまで漁獲情報は手書きの紙台帳での管理と口頭やファクスでアナログでの伝達だったが、アプリの導入によりデジタルデータ化を実現した。
アプリを開発した水産大学校海洋生産管理学科の松本浩文准教授と宮本組合長が山口県宇部市とオンラインで5日にあったはこだて未来大学主催の「マリンITワークショップ2022やまぐち」で発表した。
宮本組合長は「漁獲情報がデータとなり可視化され、管理効率が向上するなどメリットしかない。さまざまな要因があろうがアプリ導入後、魚価は確実に向上した」と高く評価する。
漁獲情報を即時集約持続可能な沖底へ
アプリのため専用の端末は不要で、スマホやタブレットに搭載できる。船上で水揚げした魚種・数量などを入力し、入港の2~3日前に卸(下関中央魚市場)へ送る。水揚げデータの公開は卸のみで仲卸は見られない。卸はセリの事前に水揚げ情報が分かることで「仲卸に営業がしやすくなった」と利点を挙げる。市場では船ごとに漁獲記録がリアルタイムで集約される。また、各船が操業する海域や水揚げ状況は他船・他社からは見られないため、各社間の情報は保持される。
漁船から陸へ入港予定時刻をメールで伝えるため、また魚函業者に箱使用状況をメールで知らせるため、補填(ほてん)する箱数やサイズを事前に準備可能となった。
アプリの導入には各船の同意や高齢の乗組員に操作指導など“壁”もあったが「松本准教授が直接現場で要望を聞きアプリをつくり込んだため使いやすい」と宮本組合長。
下関沖底と同様の2そう引漁法の島根県浜田市の沖底船団でも導入を検討中という。宮本組合長は「今後、他地域の沖合底引にも導入が進み、水産資源と漁業経営の両面で持続可能なシステムになれば」と期待する。
[みなと新聞2022年3月9日18時20分配信]
https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/
+reC. (プラスレック)がよくわかる
資料を無料でお配りしています
資料ダウンロード