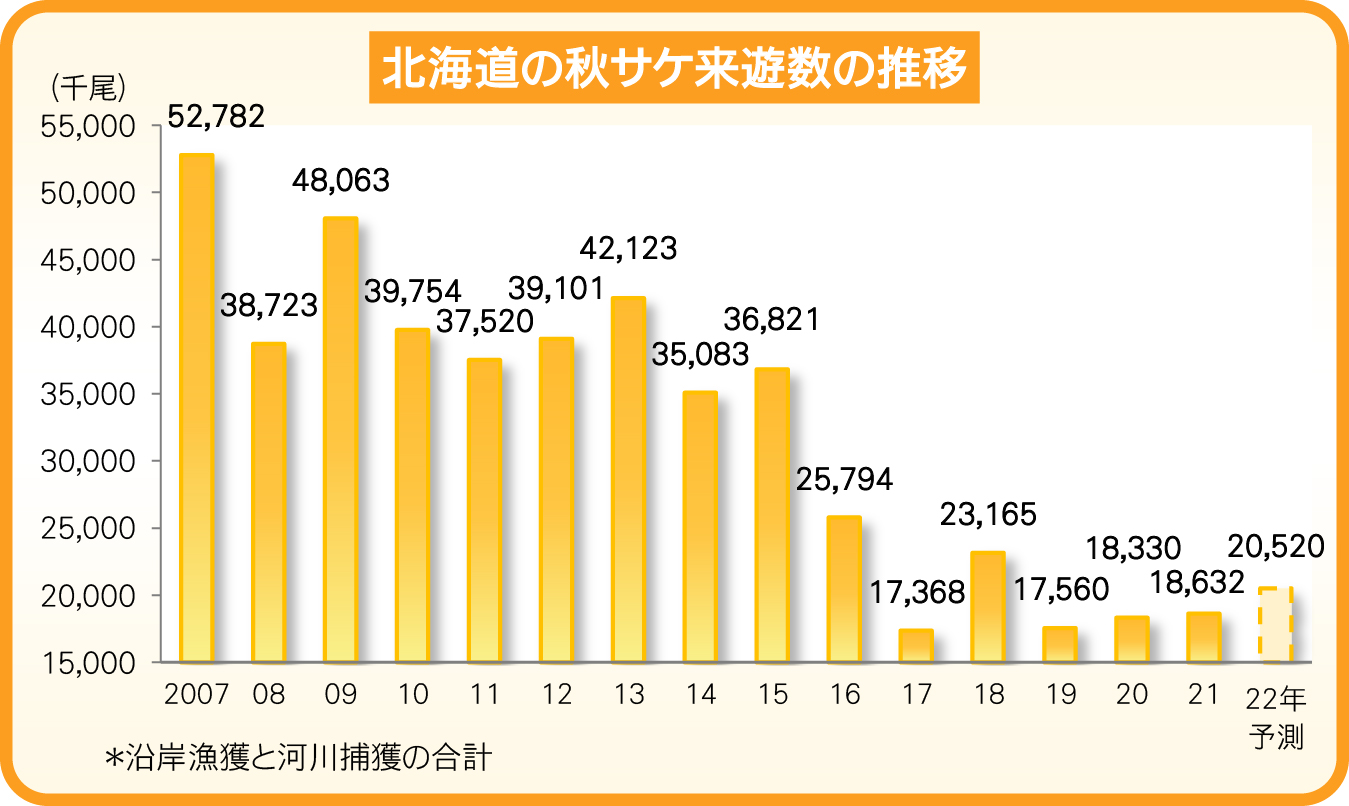自民党の水産総合調査会(小泉進次郎会長)と水産部会(鈴木貴子部会長)は16日に党本部で会合し「水産政策の新たな展開に関する提言」第1弾の取りまとめを小泉会長に一任した。石破茂首相へ申し入れて6月ごろ政府が定める「骨太の方針」に反映される見込みとなった。
海洋環境変化や資源状態を迅速に高精度で把握するための研究体制強化を筆頭に、環境変化に適応しようとする漁業への支援、漁業の協業化や法人化の後押し、水産高卒業生の就漁促進、地域資源を生かした「海業」の振興やそこに向けた遊漁管理、違法・無報告・無規制(IUU)漁業対策対象魚種の拡大などを進める内容。
2月からの同調査会水産業強靱(きょうじん)化プロジェクトチーム(PT、山本啓介座長)と海の地方創生PT(長谷川淳二座長)の議論を集約。今回は漁船漁業に特化したが、今後養殖と加工についても提言し、水産業の「強靱化計画」をまとめる予定だ。前例踏襲の連続的政策でなく、海洋環境の変化の速さに対応できる非連続的政策を目指すという。
会合後に参加議員が会見した。小泉氏は「資源の調査評価を科学的にリアルタイムでできる体制強化を最初に入れている。守りの予算から攻めの予算へ、将来への投資的な予算を獲得しないといけない」と強調。山本氏は「このままでは水産業が衰退するという危機感で、地域現場の声を聞きながらまとめた。今までの取り組みを続けたい思いは誰しもあるが、温暖化や魚価低迷で今まで通りするのもままならない。制度や規制、予算。取り組みを通じ共に変わっていこうと。水産庁だけで大きく変えることはできない、政治側から大きく突き動かす」と意思表示した。
提言の主な方向性は次の通り。
水温上昇でプランクトンがほとんど生息できない海域が生じるなど、海洋環境が激変する中、水産研究・教育機構の体制充実や漁業者からのデータ提出、国内外の研究機関の連携などを通じ、環境や資源の実態を随時捉えて、漁獲可能量(TAC)含む資源管理の実効性を高める。
環境が変わり、獲れやすい魚種や漁場も変わっているが、現状は漁船ごとのサイズや使える漁法が細かく規制されているため、現在の環境に合った操業形態に転換できるように関連規制の見直しと支援を進める。きめ細かい栄養塩管理も検討する。
漁業者の経営支援として、協業化・法人化を後押し。水産高校の卒業生や海技資格所持者の就漁を促す。就漁者に魅力的な職場をつくるため、居住環境や通信環境の整った漁船の導入を進める。
IUU対策については「漁業者からも声が大きかった。一つ項目をつくり防止策を位置付けている」(小泉氏)。水産流通適正化法で、トレーサビリティー担保対象魚種の拡大を検討する。
漁村観光など「海業」の推進に向け、モデル事例を深化。集客に役立つものの資源管理に支障を来すこともある遊漁には、規則づくり・啓発などを支援する。
海洋プラスチック対策として、廃漁網のリサイクルモデルの実証取り組みを推進。魚「食」に「職」「触」などの意も加えた「ぎょしょく」啓発を意識し、ガスグリル関連企業など民間とも協力、魚料理や掃除の手間を省く情報発信も行う。
[みなと新聞2025年5月16日17時50分配信]
https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/
+reC. (プラスレック)がよくわかる
資料を無料でお配りしています
資料ダウンロード