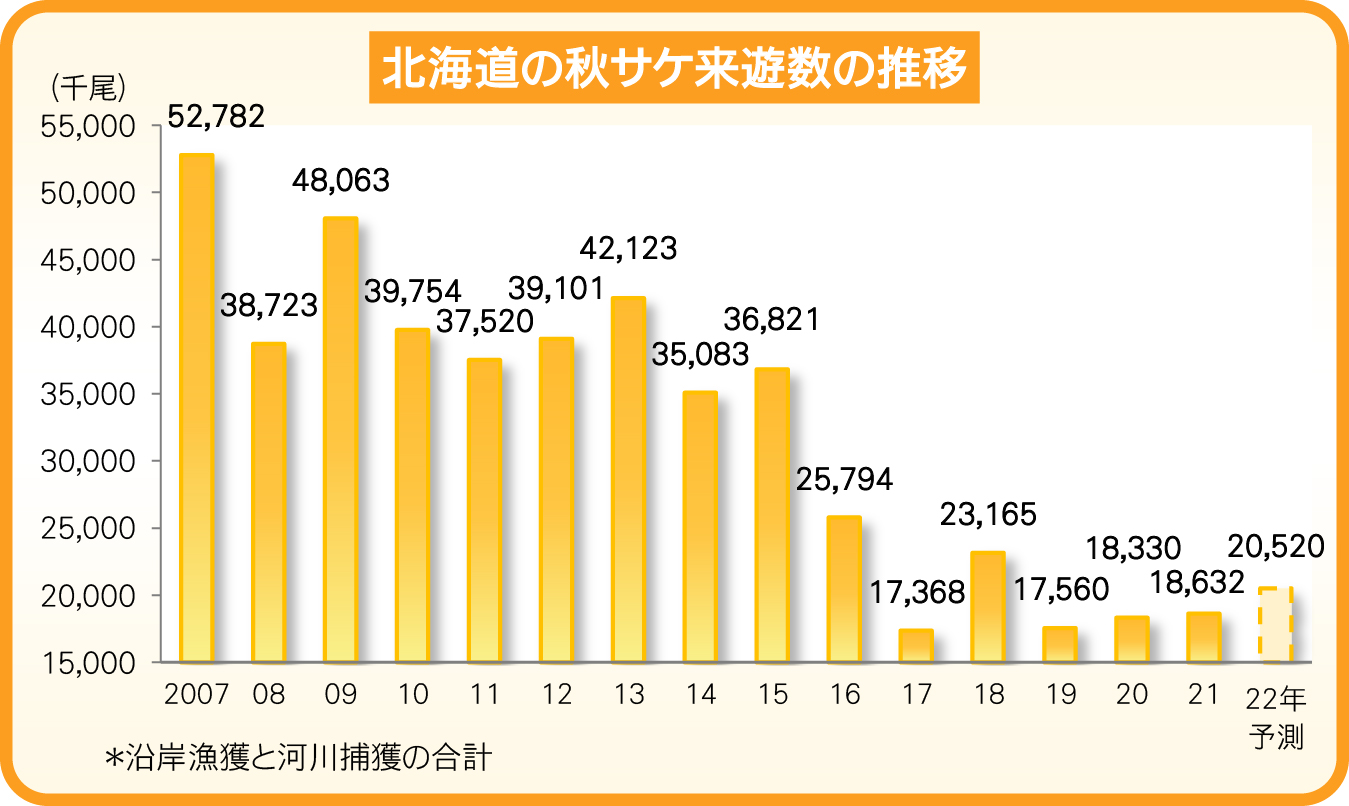水産庁が19日に開いた水産政策審議会資源管理分科会で、2025年漁期(4月~26年3月)のスルメイカ漁獲可能量(TAC)の期中改定による増枠を承認した。政府は、冬生まれ群の最新の資源調査結果や漁獲状況、研究機関の助言などを踏まえて、当初予測よりも「良好な加入(漁獲対象に加わること)が発生している」との判断の下、変更後のTACとして当初枠から6600トン増の2万5800トンを示した。
科学的根拠に疑問の声も
増枠分は国の留保とし、これから盛漁期を迎える漁法や地域に不平等とならないようルールを設けて配分する。委員からはおおむね了承を得たが、一部委員からは「科学的根拠や調査が不十分では」と増枠を疑問視する意見もあった。
近年の資源悪化を背景に、政府は25年漁期のTACを24年漁期比で76%減の1万9200トンと大きく引き締めた。ただ、スルメイカは寿命が1年と短く資源量の変動が激しいことから、農林水産相が「良好な加入」が発生していると判断した場合は速やかにTAC数量変更の手続きを行うとの規定を盛り込んだ。
今シーズンは主に三陸沖で、近年より漁獲がまとまっている。国は留保分から枠を追加配分して対応するが、一部漁法では漁獲調整や休漁措置を講じるなど枠の不足を訴える声が上がっていた。
7~8月 三陸域で低迷前CPUEに迫る
水産研究・教育機構は同庁からの依頼を受け、冬生まれ群の資源量推定に用いる小型イカ釣(小イカ)の漁況について、7~8月の太平洋三陸域(青森県八戸、岩手主要港、宮城主要港)のCPUE(釣機1台1時間当たりのスルメイカ採集尾数)を検討した。この結果、地区合計のCPUEは前年と直近5年間の水準を上回り、相対的にも資源量が低迷する前の14年と同程度だった。
ただ、検討には道東・太平洋域の盛漁期である9~10月を含まず、対象地域も三陸域に限定される。そのため25年の加入については、小イカCPUEの不確実性やこれまでの調査結果を踏まえ、「直近5年間の中では高水準にある可能性が高いとみなすのが妥当」とした一方、現時点では14年と同程度とは言い切れないとも留意した。
水産庁は25年漁期の当初TAC設定にあたり、冬生まれ群の予測加入量の平均値について「近年の低加入が続く」と仮定して15万トンとしたが、最新調査のCPUEは1980年、99年、2001年、02年、10年、14年と同水準だった。各年の加入量は49・3万~87・5万トン、平均で69・7万トン。水研機構が昨年示していた、良好な加入があった場合のシナリオ予測値の42・1万トンを超える。
水産庁は現在、資源が激減した冬生まれ群について資源再建計画に基づいた管理を行う。最低目標である限界管理基準値(14・5万トン)を暫定的な管理基準値とし、34年にこの基準値を上回る確率が50%以上となる漁獲シナリオ(漁獲ペース〈安全係数〉β=0・5)を採用している。増枠に当たっては、水研機構の試算による加入量の予測値(42・1万トン)を前提に、β=0・5で算出した生物学的許容漁獲量(ABC)に基づき当初枠から6600トン増の2万5800トンを示した。
なお、同庁は増枠に当たり、「資源の着実な回復を妨げるものではない」との考えを示す。根拠として、今年7~8月の小イカのCPUEから考えられる加入量(49・3万~87・5万トン)よりも控えめな加入量の予測値(42・1万トン)を根拠に算出したABCを使ったこと、βを変えていないことを挙げた。
スルメイカ加入悪化で減枠も
委員から検証求める声
漁獲枠に不足感が漂う中、漁業関係の委員からは産地での窮状を訴える声が上がり、増枠を歓迎した。イカ釣漁業関係の委員からは「最低限の経済を維持するために今回のTAC追加に賛成したい」との意見があった他、「資源評価の不確実性の高いTACで漁業者を死活問題に追い込むことは本末転倒」などの意見、より柔軟なTAC運用を求める声があった。
定置網漁業関係の委員からは「今回の提案を否定するわけではない」と前置きした上で、漁獲枠の期中改定が他魚種に拡大して「MSYにのっとり資源管理すると明文化されたことがほごにならなければいいが」と懸念する声、資源状況が悪いと判断された場合には減枠する場合もあるかと問う場面があった。
同庁は、TACの期中改定は寿命が短く資源評価が難しいというスルメイカの特性を踏まえた規定であることを説明。漁期中に加入が悪いと判断された場合には、期中に減枠することもあるとした。
水産流通業界の委員からは、水産庁が示したデータについて、調査時期や海域が限られることを指摘。「黒潮大蛇行が弱まり、一時的に局地的にイカが集まってきた可能性も否定できないのでは」と言及し、増枠に当たり、「科学的根拠や調査がまだ不十分では」と慎重な姿勢を示した。
今回の期中変更の決定について、「スルメイカのみならず日本の水産資源の管理や評価に重要なこと。この決定が正しいものであるか、半年後や1年後に検証する必要がある」とも訴えた。
同庁は増枠の根拠として、βを変えずに管理を行うこと、加入量の予測値を控えめな42・1万トンとして試算したことを説明して理解を求めた。
複数の委員からはその他、資源評価の精度を上げるため、最新の水揚げ状況などリアルタイムな情報を踏まえて評価を行うことが重要との指摘があった。
[みなと新聞2025年9月22日17時50分配信]
https://www.minato-yamaguchi.co.jp/minato/
+reC. (プラスレック)がよくわかる
資料を無料でお配りしています
資料ダウンロード